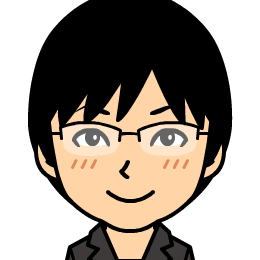「ゲーミングPCって何が特別なの?普通のパソコンとどう違うの?」と疑問に思っていませんか?
ゲームをパソコンで始めてみたいけれど、専門用語ばかりで難しく感じてしまう…。そんな不安を抱えている初心者の方は意外と多いです。
実際、筆者の友人たちも「ゲーミングPC=高い・難しそう」というイメージから、なかなか一歩を踏み出せずにいました。
でも安心してください!この記事では、ゲーミングPCとは何か、その違いや使い方、後悔しない選び方までを、パソコン初心者でもわかるようにやさしく解説しています。
これまで筆者が紹介してきたゲーミングPCは、「初心者でも迷わず選べた!」「快適にゲームができるようになった」とさまざまな方から高評価をいただいています。
「ゲーミングPCって結局どうなの?」という疑問は、この記事を読めばスッキリ解決。最後にはおすすめの選び方や注意点もしっかりまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください!
ゲーミングPCとは?まずは基本をわかりやすく解説

ゲーミングPCとは、ゲームを快適に遊ぶために作られた高性能なパソコンです。
普通のパソコンでもゲームはできますが、動きがカクカクしたり、画質が悪かったりしてストレスになります。ゲームは映像や音がリアルでスムーズであることが大切。
そこで、より強い「グラフィックボード」や「高性能なCPU・メモリ」を備えたパソコン=ゲーミングPCが必要なのです。
たとえば、マインクラフトやフォートナイトを遊ぶとき、普通のノートパソコンでは処理が追いつかず、動きが止まってしまうことも。
ゲーミングPCなら、60fps~240fpsなど高いフレームレートで、ぬるぬる動く映像を楽しめます。しかも画面がきれいで反応も速く、まるで本当にその世界に入っているような感覚になります。
つまり、ゲーミングPCはただ「ゲームができる」だけでなく、「ゲームを最高に楽しむため」の特別なパソコンなのです。
どんな人にゲーミングPCが必要?
ゲームだけでなく、動画編集や配信などをしたい人にもゲーミングPCは必要です。
ゲーミングPCは「処理が早くて、映像がきれい」なので、ゲームだけでなくいろいろな作業に向いています。
たとえばYouTube動画の編集や、ゲームのライブ配信など。重い作業もサクサクこなせるのが特徴です。
ゲーミングPCはこんな人におすすめ!
- FPSや格闘ゲームを本気でプレイしたい人
- マイクラなどMODを入れて遊ぶ人
- TwitchやYouTubeでゲーム配信したい人
- 動画編集や3Dイラストなどをやりたい人
また、PS5やSwitchと違って、ゲーム向けの高性能マウスやキーボードで操作できる、MODで自由にゲームを改造できるなど、パソコンならではの遊び方もできます。
「ゲームをもっと深く楽しみたい」「動画編集や配信もやってみたい」そんな人にこそ、ゲーミングPCはおすすめです。
ゲーミングPCでできること・できないこと

ゲーミングPCはとても多機能ですが、万能ではありません。
ゲーミングPCはゲームや映像に強い反面、スピーカーがなかったり、持ち運びがしづらかったりすることもあります。
つまり「できること・できないこと」を知っておくと後悔しません。
■ゲーミングPCでできること
- 高画質ゲームのプレイ
- 動画編集・イラスト制作
- ライブ配信・マルチタスク作業
■ゲーミングPCでできないこと(注意点)
- ノート型はバッテリーの持ちが短い
- スピーカー非搭載モデルもある(要ヘッドセット)
- 大きくて重いので持ち運びに不便(デスクトップ型)
ゲーミングPCの得意なこと・不得意なことを知って、自分の使い方に合っているかを考えることが大事です。
ゲーミングPCはいくらで買える?価格帯と性能の目安
ゲーミングPCは「10万円〜30万円以上」と幅広く、自分の遊びたいゲームや目的に合わせて選べます。
使うゲームによって、必要な性能が変わります。
たとえば、軽いゲームなら10万円台のPCでも十分ですが、最新の3Dゲームや配信もしたいなら20万円以上のモデルが必要になることもあります。
10万円前後:エントリーモデル
- マインクラフトや軽めのゲームならOK
- フルHD・中画質で快適に遊べる
- 「とりあえず試したい」初心者向け
15〜20万円:バランス型ミドルクラス
- Apex Legends、Valorantなども快適に動作
- WQHDや高画質設定も対応できる
- 「コスパ重視」や「迷ったらこれ」で選ばれる定番
25万円以上:ハイクラスモデル
- 4Kや144Hz以上のリフレッシュレート対応
- 動画編集、配信、マルチモニターも余裕
- 「ゲームも作業も全部本気でやりたい人」向け
「遊びたいゲームがサクサク動くかどうか」で価格と性能を選ぶのがポイント。目的に合った予算で選びましょう。
ノート型とデスクトップ型、どっちがいい?

初心者は基本的にデスクトップ型がおすすめですが、使う場所やスタイルによってはノート型もアリです。
ノート型は省スペースで持ち運べるのが魅力。デスクトップ型は性能が高くて価格もお得。ただし、それぞれにメリットとデメリットがあります。
■ノート型のメリット・デメリット
コンパクトで場所を取らない
電源を入れたらすぐ使える
持ち運びやすく、外出先でも使える
性能に限界がある(特にグラフィック)
熱がこもりやすく、うるさいこともある
価格が高めで、拡張しづらい
■デスクトップ型のメリット・デメリット
高性能でも価格が安い
パーツ交換やアップグレードが簡単
冷却性が高く、安定して動作する
場所を取る
持ち運び不可
設置や配線が少し面倒
「どこで、何に使うか」が選ぶカギ。据え置きで快適に遊びたいならデスクトップ。移動したいならノートが便利です。
どこで買う?初心者におすすめの購入先とメーカー
初心者には「BTOパソコンショップ」が安心でおすすめ。自分に合った構成を選びやすく、サポートも充実しています。
BTO(Build To Order)とは、「注文に応じて組まれるカスタムPC」のこと。
すでにパーツのバランスが取れていて、初心者でも安心して選べます。さらに保証や修理サポートも充実しています。
■おすすめBTOメーカー
- ドスパラ(GALLERIA):初心者向けセットが豊富
- マウスコンピューター(G-Tune):信頼の国内メーカー
- パソコン工房:コスパに優れたモデルが多数
■Amazon・家電量販店はどう?
- すぐ手に入るのはメリット
- ただし、スペックのバランスが悪い場合もある
- サポートや拡張性が限定されることも多い
「初心者だからこそ、安心して買える場所で」買うことが大切。BTOショップの公式サイトなら、後悔しにくい選び方ができます。
自作PCと完成品、初心者はどっちを選ぶべき?

初心者には「完成品ゲーミングPC」が断然おすすめです。自作PCは確かに安く組める可能性がありますが、パーツの知識や組み立てスキル、トラブル対応力が求められます。
一方で、完成品は最初から動作確認済みで安心して使えます。
■自作のメリット
- パーツを自由に選べる
- 価格を抑えられる場合もある
- パソコンの仕組みを学べる
▲自作のデメリット
- 組み立て・配線の知識が必要
- 起動しないときの対応が難しい
- 保証やサポートが分散する(各パーツごと)
■完成品の特徴
- すぐに使える
- パーツの相性問題がない
- メーカー保証がしっかりしている
安心してゲームを楽しみたいなら完成品。まずは完成品でスタートし、慣れてきたら自作に挑戦するのもおすすめです。
買った後に後悔しないために|ゲーミングPC選びの注意点
スペックのバランスやサポート体制、将来の拡張性まで考えるのが後悔しないコツです。
高いパーツばかりを集めても、ボトルネックがあると性能を活かせません。また、修理やサポート体制がしっかりしていないと、いざという時に困ります。
■よくある失敗例
- 高いグラボを選んだのに、CPUが足を引っ張っていた
- 電源の容量不足で安定しない
- 保証が短く、すぐにトラブルになった
■チェックポイント
- グラボ・CPU・メモリのバランス
- メーカー保証とサポート内容
- ケースの大きさとパーツの交換可否
- 拡張性(M.2や空きスロットの有無)
性能だけでなく、「長く安心して使えるか」にも注目して、バランスの良いゲーミングPCを選びましょう。
まとめ:ゲーミングPCとは「高性能な自由空間」
ゲーミングPCは、ただゲームを楽しむためだけのパソコンではありません。
高性能なパーツを活かして、動画編集やライブ配信、イラスト制作など、幅広いクリエイティブ作業にも対応できる、まさに“多機能な万能ツール”です。
一見すると「初心者にはハードルが高そう」と感じるかもしれませんが、この記事で紹介した選び方や注意点を押さえれば、自分にぴったりの1台を見つけるのは決して難しくありません。
大切なのは、「自分がやりたいことに対応できるか?」を基準にしながら、価格・性能・サポートのバランスをしっかり比較することです。
信頼できるメーカーやサポート体制が整ったモデルを選べば、初めてでも安心してゲーミングPCデビューができます。
さあ、あなたのやりたいことを思いっきり叶えてくれる“最強のパートナー”を手に入れて、理想のPCライフをスタートしましょう!